沢栄の「さらばニッポン官僚社会」
| ■Online Journal NAGURICOM 沢栄の「さらばニッポン官僚社会」 |
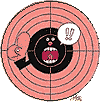
第77 章 業務の他律性と給与の自律性 ー 独立行政法人
(2004年10月28日)
独立行政法人(独法)制度が2001年4月に導入されて以来、最初の山場に差しかかっている。政府は05年度末までに中期目標期間が終了する1期生の56法人のうち32法人について、計画を前倒ししてことし中に「組織形態と事務・事業の見直し」を行う、としたためだ。「初の徹底的な見直し」(総務省)とあって、独法の現場にピリリと緊張感が走る。
見直し作業には、この9月から内閣の特殊法人等改革参与会議も有識者会議の形で関与する。行政改革の新手法として登場した独法だが、官は既に特殊法人以上の「蜜」を独法から吸い上げている実態は第75章などで紹介した。迷走する独法を果たしてまともな軌道に乗せられるか、― 監視・評価を担う府省と総務省の独法評価委と有識者会議の腕前が試される。
32法人を見直し
この10月で独法の設立数は国立大学法人の89を除き、計108法人に上る。
道路公団民営化に向け、05年度中に独法の日本高速道路保有・債務返済機構が設立される。06年4月には特殊法人・年金資金運用基金が独法化し、年金積立金管理運用独立行政法人が設立される。約150兆円にも上る年金積立金の管理・運用を独法が手掛けることになる。
こうして独法は行革の新手法として盛んに活用され、今後も増える見通しだ。
今回、32法人に対して行われる「組織形態と事務・事業の見直し」の視点は、業務面で、1. 事務・事業の必要性・有効性、2. 実施主体の適切性、3. 効率化、質の向上などの達成状況、である。
これを踏まえ、1. 事務・事業の廃止、2. 民間または地方自治体への移管、3. 事務・事業の制度的独占の廃止、4. 自主財源の拡大、補助金依存度の引き下げ、5. ほかの独法または国への移管、6. 民間委託の拡大、7. 整理縮小、8. 市場化テスト(事務・事業の入札を民間から募集し、独法よりコスト面などで有利な場合は委託)、などを検討する。結果、必要性が認められなければ、法人自体の「廃止」または「民営化」を考える、というものだ。
見直しで、独法の事業実態に初めてメスが入るわけだが、独法の現場では、早くも役員と一般職員との間で不協和音が鳴り響いている。入社して間もない職員が、デタラメな役員の言動にホトホト手を焼いている光景が見え隠れする。「勤め感覚」の埋めがたいギャップが、民間に就職経験のある良識派の職員を大いに戸惑わせているのだ。
独法の実態を把握するために、まずはこの現実の出来事を読者にお知らせしよう。
むろん、これをもって全部の法人が似たような状況にあるとは思わないが、独法の業務には内部の勤労規律を蝕む“危険因子”が潜んでいるとみられるのである。
役員秘書の困惑
筆者が独法の役員秘書から受け取った匿名の内部告発メールが、独法の体質に目を向けるきっかけとなった。
この発信者は、当「NAGURICOM 」をみて、ことし5月と7月の計3度にわたり、独法の役員の勤務実態について伝えてきた。
勤め先は「ある独法の研究所」としか言わないが、本省から天下りしてきている役員は全部で5人、「53歳、56歳」といった、働き盛りの早期退職者で占められている。
「(元官僚の役員が)海外出張から帰ったのですが、出張にかかった費用の請求に必要なチケット等の提出にゴネ、『なぜ必要なのか?何に使うのか?前(官庁)のところでは一回も提出なんてしたことがなかった』と、企業では考えられない発言をされていて、私にはそういう疑問をされるほうがわからないと思えました」(原文ママ)。
チケットやパスポートのコピーも提出しようとしないため、秘書は思い余って経理部に頼み、前職の官庁に問い合わせて処理をどうしていたかを聞いた。すると「なんとかしていた」という答えが返ってきたという。
この役員は安チケットを購入したのかもしれない。前任の官庁でカラ出張していた疑いもあながち否定できない。メールは、訴える。
「ファイル類など事務用品も腐るほど大量買いするのか、秘書室用に大量に保管されています」「日中はインターネットにネットゲーム、夕方は電気と冷房をガンガンつけて楽しい飲酒ですから。その飲酒体質は全体的なものであり、ほとんど外に行くことはなく、節電なんて何のその、事務職すら同じ状態で所内で居酒屋状態です、毎晩。私は以前、大手の企業にいたこともあり、会社内での飲酒も見たことがないわけでもなく「盗賊の酒盛り」はありました(私ではなく男性社員ですが)が、状況はかなり違います」(同)
秘書の目で間近に見ると、民間企業では考えられない実態なのだろう。
「正直言いまして、このような実態を見るまでは、特殊法人など特に興味も疑問もありませんでした。・・・身近に見るようになり、この国の根本の腐りを感じます」(同)
こういうデタラメ役員に「規律」を植え付けるためにも、厳しい見直しが欠かせない。
独法の構造問題
この秘書の“告発”にみるように、多くの独法で役員のモラルが問題になっている。なぜ、モラルの低下をきたすのか?
筆者はこれを独法の「構造上の問題」と考える。その理由は、独法の看板にある「事業の自律性」とは逆に、実態は「他律的」だからである。所管省庁の顔色をうかがって、決められた通りに動く。そういう自己決定しない習い性がどの法人にも認められるのだ。
一例を挙げると、独法には「業務運営の効率化に関する目標」という数値目標がある。これに対して、例えば水産大学校は次のように自慢する。
「中期目標の期間中、人件費を除き毎年度前年比1%の経費削減を行うこととしており、毎年着実に達成している」
だが、この「人件費を除く毎年度1%経費削減目標」は、実は水産大学校が自ら決めた数値目標ではない。口裏を合わせたように、どの独法も掲げる目標値だ。つまりは、役所が指導して一律横並びで決まったものだ。
民間企業でデフレ下の経費節減目標をわずか「年間1%減」にしている企業はあるだろうか。それも、自分たち用の人件費をちゃっかり除いて、である。
独法の運営費の大半を占める補助金の「運営費交付金」(04年度予算計1兆5445億8400万円)。役職員の人件費はすべてこの交付金から賄われるが、その節減は「しないでいい」と例外扱いにし、自分たちの人件費は自分たちで決められる「聖域」になっているのだ。
総務省7月の発表によれば、独法制度は「国の事前関与を必要最小限とし、法人が自律的な業務運営を行うことを基本とする」ため、「法人の役員の報酬等および職員の給与については、法人の自律性の尊重の下、国家公務員や民間企業の給与、法人の業績等を考慮しつつ、各法人がそれぞれ支給基準を定めることとしている」(下線筆者)とある。
つまり、給料や賞与は、自律性を尊重して自己決定できる、というのだ。結果、コスト減の対象から外し、自分勝手に決めるようになった。
総務省は「国家公務員や民間企業の給与等」を考慮して決めるように、と注文を付けてはいるが、現実は全法人がこれを無視した。第75章で指摘したように、独法職員の年間給与総額は国家公務員よりも多いのだ。
役員報酬も、理事長で平均して本府省の「局長並み」(約108万円―99万円)と、高め設定されてある。こうした事態は、閣議決定された内閣の方針を各府省庁が揃って無視して、独法に好きなようにやらせた結果生まれたのだ。官の暴走というほかない。
役員13人全員が天下り
このように、業務については国の言いなりと他律的だが、給与だと「自律性の尊重」をタテに自らの裁量で決める両面が独法にある。一種のねじれ現象だが、ここから生まれる国(府省庁)に対する被抑圧感(他律性)とうさ晴らし感(自律性)というコンプレックスが、先の告発メールに登場する役員のうっ屈した心情になるのではなかろうか。
となると、元エリート官僚のある種の被害意識が理解できるような気もする。彼らのモラル低下は「行政組織が生んだ精神的抑圧の産物」なのであり、本省従属意識と業務の他律性がつくり上げた代物にほかならないのだ。
公務員の早期退職勧奨慣行の下で、50歳代半ばまでにキャリア官僚の半分以上が退職していく。当然、その多くが受け皿の独法に流れ込む。ことし1月時点で独法の職員数は92法人で4万人以上に上る。その大部分はむろん退職公務員だ。
特殊法人改革の切り札とされた独法だが、理念はともかく現実は早期退職する官僚の、特殊法人に代わる「受け皿」の役割を果たしてきた。だからこそ、公務員と特殊法人のような準公務員の退職者を合わせた役員の天下り比率は、全役員の96%にも上る。特殊法人よりも、天下り比率が高いのだ。
役員全員を天下り官僚が占める独法も数多い。農業・生物系特定産業技術研究機構(農林水産省所管)の場合、なんと役員13人全員が官僚OBだ。
こういう官僚OB集団が、本省から「独立した業務として自主的に考えてやれ」といわれても、建て前のようにはなかなか行かない。筆者の取材に対してさえ、「本省が対応する」と逃れ、実際に農薬研究所に代わって農水省が、酒類総合研究所に代わって財務省が対応してきた。まるでオンブにダッコだ。独立行政法人として気概と責任感をもって取材に応じる気風さえ欠いているのである。
政府による組織形態と業務の見直しは、それ自体、独法役員の萎えたモラルにも活を入れることになろう。活が入らなければ、既に死に体状態の組織は、もはや蘇生できそうにない。時代の流れでかつての役割を終えたり、民間や地方自治体でも同様の事業を行っているため、国家の実施機関として「存在意義」を失った法人が少なくないためだ。
廃止すべき法人
これまでの経緯から、見直し作業は類似事業の統合を軸に論議が進みそうだ。
筆者は要らなくなった独法は他の独法と統合させるのではなく、「法人自体を廃止」すべきだと考える。過去において、統合は組織の肥大化を招いてきたからだ。廃止の際、民間や地方自治体に移管できる事業は移管すればよい。
「民営化」も選択肢から外すべきだ。なぜなら、前身が国の直営事業だったり特殊法人だった独法は、民営化しても商業ベースでの成功は、行政需要に結び付かない限り土台ムリだからだ。ムリに民営化すれば、行政の委託や下請け事業となり、行政密着型の公益法人やそのファミリー企業と変わるところがない。
そこで、独法に一体「存在意義」があるのかどうか、がまず問われ、「ノー」ならば、法人自体を廃止して肥大化した政府系機関を整理するべきである。
廃止の基準としては、時代を経て既に存在意義を見出せなくなった法人に加え、本来の事業目的を毎年達成できず、今後の運営のメドも立たない法人が考えられる。
官業の失敗で多額の損失を出しいったんは「廃止」が決まったが、独法化して看板を掛け替えた旧特殊法人も廃止候補となる。旧雇用促進事業団を廃止して衣替えした雇用・能力開発機構(ことし3月独法化)と、年金資金運用に失敗して廃止された旧年金福祉事業団を改組した旧年金資金運用基金をさらに独法化した年金積立金管理運用独立行政法人(06年4月に設立予定)が、これに該当する。
これらのゾンビ法人は、世論の批判を浴びて「独法」の敷地に緊急避難してきたのだ。独法で再び「存在意義」を問うのが、行革の筋道である。
旧特殊法人・労働福祉事業団が、ことし4月に名称を変えて独法化された労働者健康福祉機構も、いずれ廃止の可否が検討されるべきだ。同法人は労災保険の積立金を財源に事業運営しているから、保険金給付以外の事業に保険財源を使ってよいかどうか、が改めて問われなければならない。
民間企業は時代の波に取り残されたり、ほんろうされて転覆・消滅を強いられるが、公的機関は役割を終えても、事業を追加して組織延命を図る。「小さな政府」実現には強力な政治のリーダーシップが欠かせないが、国民にとっての不幸は、小泉自公政権が、官を焼け太らせる、形だけの改革しか実行しないことだ。