| ■Online Journal NAGURICOM 沢栄の「さらばニッポン官僚社会」 |
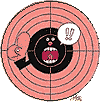
第9章 マスコミ首脳が行政改革に水をさす―背後に絡む?再販問題
21世紀の「この国のかたち」となる中央省庁再編法(2001年1月施行)を決めた行政改革会議(会長・橋本龍太郎首相、肩書きはいずれも97年12月当時)の「マル秘」印の付いた議事録を追っていくと、思わず首をかしげてしまう場面がある。これまでの論議に突然「飛躍」が起こり、いつのまにか改革の例外扱いという「結論」が出されてしまっていることだ。なぜ「例外扱い」になったかの明確な説明はない。そのはず、自民党や官僚からの圧力とか、行革会議委員自身が業界の利益代弁者として改革論議を骨抜きにしてしまうためだ。
文化庁の「例外扱い」を働きかける
その一例が、行革会議委員を務めた渡辺恒雄・読売新聞社社長・主筆と、川口幹夫・NHK顧問(97年7月まで会長)が二人三脚で委員会に働きかけ、結果として国営事業・事務スリム化の目玉とされた「独立行政法人化」をごく“小物”ばかりに終わらせてしまったケースだ。マスコミの二大巨頭が、著作権の所管官庁である文化庁を例外扱いとし、独立行政法人化の対象から特別に外させたことで、いったんは本省からの分離を内諾していたはずの食糧庁、林野庁、水産庁など他の庁も、文化庁と同様の「例外扱い」を要求して、結局全ての庁を存続させることとしてしまったのである。そして、「とりわけナベツネさんが文化庁を例外扱いにしようと熱心に働きかけたのは、新聞の再販制度を維持しようと、この際文化庁に恩を売っておこうとしたためではないか」と委員らの間に疑念が広がったのである。
この経緯は、マスコミの利害に絡んでいるせいか、これまでに一切報道されていない。一つ、はっきりしたことは、巨大言論機関のトップが「言論の自由」を守る名目で、業界の利益を横並びで代弁し、主張するような場合、真実が報道される機会は事実上閉め出されてしまうことだ。
“骨抜き”の序曲は、97年10月22日の第33回行革会議に提出された川口幹夫氏の「意見メモ」に始まる。川口氏はこの日、ソウルで開催されているアジア放送連合(ABU)の総会に出席するため、行革会議には欠席せざるを得ないとして、文書で意見書を出した。それは、「文化行政について」次のように述べている。
「かつて文化庁が誕生し、今日出海氏が初代の長官に就任した時は、新鮮な共感を覚えた。その後の文化庁の仕事ぶりが期待に応えているかといえば、必ずしもそうと言えない憾みがあるが、国際的な親和性の向上と日本人としてのアイデンテティの確立という難しい課題を両立させるためには、文化というものがいっそう重要なカギになる。外局の定義に引きずられ、内局に埋没させるのはいかがなものか。外局として維持し、姿勢を示すべきであると考える」
ここで問題点を浮き彫りにするために、当時、英国のサッチャー首相が実行したエージェンシー制(外庁化)を手本に、行革会議がどういう改革の構想を抱いていたか、を示しておこう。行革会議の会長を務めた橋本首相の「補佐官」兼「行革会議事務局長」兼「委員」という地位で行革会議を推進した水野清氏に近い筋によれば、水野氏は日本版エージェンシーに当たる独立行政法人化を進める手順として次のように考えていた。
まず、文化庁などの外庁を本省から「実施庁」として分離させる(企画立案部門は本省に残る)。次に、究極の目的である外庁の独立行政法人化を狙う。英国の例でも、行政改革の仕上げの段階で政府の持つ実施機能(現場機能)のエージェンシー化が広範囲に断行されている。
水野氏側は、水面下の折衝で内々には農水省から三庁(食糧、水産、林野)について「応諾」の感触を得ていた。通産省の外局である資源エネルギー庁、中小企業庁はこの段階で難しくはあったが、不可能ではなく、流動的であった。消防庁はまだ検討の対象外にあり、防衛施設庁は是が非でもやりたかった。
こういうデリケートな始動の局面で、何よりも必要な「まとめのテクニック」は、内諾したところからまず公表し、これを突破口に将棋倒し的にバタバタと決めてしまうことだ。非常に難しい案件は後回しにするに限る。
ところが、事態は逆に動いた。川口氏の「意見メモ」をきっかけに、渡辺氏が文化庁特別扱い論をぶち上げる。「意見メモ」から7日後の第6回企画・制度問題及び機構問題合同小委員会でのことだ。
「文化庁にならえ」と他にも波及
同小委員会で次のようなやりとりがあった。(委員の河合隼雄・国立日本文化研究センター所長、猪口邦子・上智大法学部教授らが「文化庁例外扱い」の必要論を主張したあと)
水野事務局長―これを例外にすれば、私も例外にとみんな言ってくるので、その線引きをどうしますかという問題なんです。文化庁を例外にしなければならないのであれば、エネ庁もそうだし、中小企業庁もそうだし、消防庁もそうだと。
渡辺委員―文化庁は企画立案と実施部門とを分割し難い。一心同体であるという面がかなりあるわけです。(文化庁は)文化部と文化財保護部、部としては二つしかなくて、後は官房があるだけで、小さな役所ですけれども、例えば著作権問題というのは非常に難しい問題で、これからマルチメディア時代に入ってきますと、我々も例えば放送局などでも弱っているわけです(このあと企画立案と実施機能を分けると著作権料の問題などに対応できない、との説明が続く)。…それと国際的な問題ですね。フランスなどは文化省があるくらいで、日本にはそれがないのかと。文部省があるというけれども、文部省は今度は科学技術庁と一緒になるので、非常に学術的な色彩と教育的な色彩が強くなります。それと離れて文化というもの、日本の象徴、日本文化を守るという見地からみれば、国際的な角度も考慮する必要もあります。どう考えてもほかの外局と比べて特別扱いしていいのではないかなという気がします。
川口委員―私も渡辺委員に全く賛成であります。文化庁というのは、戦後できた役所の中では大変ユニークな存在だったんです。それはまさに戦争をしないと決めた日本の生き方を象徴するような庁だったので、相当希望をかけられていたという気がします。ところが実際上は文部省の中に入っていると、教育予算に全くしわ寄せされて。誠に情けない国家予算なんです。フランスの大体26分の1以下という予算しか持っていない。辛じて今は外局の形を保っているんで、文化庁というイメージが生きているところがあるわけです。今度文部省自体が変わっていくと、さらに小さな位置付けになってしまう。これではその存在意義も何もなくなってしまうので、日本の一つの生き方の象徴として文化庁は外局として一つの形を残すべきだと。形を残すことによって仕事自体にも充実したものが出てくるということを期待すべきではないかと私は思います。
藤田宙靖委員(東北大法学部教授、議長役)―いずれにしても、文化庁は外局として政策機能も残すと。理屈はともあれ、これは大体一致があると思うんです。
というふうに展開して、文化庁は現状のまま残すことが決まる。だが、文化庁の特別扱いの結果、どの外庁も「文化庁にならえ」式に「現状維持」を要求し、通ってしまったのである。このへんの事情が、97年11月18日の第38回行革会議(集中審議2日目)で語られている。
諸井虔委員(秩父小野田株式会社取締役相談役・地方分権推進委員会委員長)―…そもそも文化庁に企画立案を認めたところから、外局というものはどうも企画立案を持ったものであり得るということになってしまって、そうなるとみんな横並びでということになって、結局今のまま元のもくあみということになってしまったわけですね。
水野委員―ですから、私もあの時、あっと思ったんですが、文化庁は認めたけど、そうすると全部に波及するかなと思って。
特別扱いを通したウラには再販問題?
日本の放送と新聞を代表する巨頭が、文化庁の特別扱いを通したウラには、何があったのか。渡辺氏は当時、日本新聞協会理事として再販対策特別委員長を務めている。当然、新聞をはじめ雑誌、著書、CDなど著作物の再販制度を維持しようとする側の急先鋒である。他方、文化庁は再販制から著作物を外すことに猛反対している。
双方の利害は一致する。となると、渡辺氏らの文化庁擁護論を再販制維持のための仕掛け、と理解するのはごく自然である。
前年の96年6月5日に衆院で開かれた「規制緩和に関する特別委員会」。ここで参考人として呼ばれた渡辺氏は、はじめこそ再販制度適用により消費者が受ける利益などについて冷静に話していたが、そのうち感情をむき出しにして、同委員会に参考人として出席している再販見直し論者の金子晃・慶應義塾大法学部教授を攻撃している。
渡辺参考人―また、今公取委員会の金子さんの属しておられる委員会というものは、非常に偏見に満ち、新聞を何とかつぶしてやりたいと思っておられるとしか思われない。三人のイデオローグがおりまして、ここの金子さんを初めとして、親委員会の鶴田という委員長と三輪という東大の教授と三人がおりますが、それが、まあ、きょうもおまきになったかどうか知らぬが、「三田評論」その他を使って、ミニコミを使って新聞に対するあらゆる悪罵を続けているわけであります。…
という具合に、魔女狩りふうに三人をこきおろしたあと、会議録によれば、別の議員の質問に対し、ある重要な事実を漏らしている。
先ほどもこの(再販制見直しの公取委)中間報告をつくった人々、そのイデオローグの紹介もいたしましたけれども、それに対して私どもが、新聞、出版社等みんな反対でありまして、文化庁とともに活字文化懇談会という組織をつくり、そこで見解を表明し、それに従ってキャンペーンをやったことは事実でありますが、つまり、新聞協会は再販外しを阻止するため文化庁の力を借りて公的な「懇談会」を設置し、官民合同でキャンペーンを続けてきたわけである。
こういう背景を知ると、二人のマスコミ首脳がどうして行革会議で文化庁の特別扱いを強硬に主張したか、の答えが浮かび上がってくる。
著作物の再販制維持が妥当かどうかで、意見が分かれるのは当然だ。しかし、業界の利益に反するから、と再販見直し論の紙面掲載を故意に見合わせ、再販制擁護論者の有名文化人の意見ばかりを紙面で紹介し、世論の支持に訴えるのは公平さを著しく欠く。さらに、21世紀の行政の骨格を決める重要会議で、委員の立場にありながら自らの利益を代弁するがゆえに文化庁を特別扱いしたとすれば、この国のマスコミの信頼性は地に堕ちても仕方あるまい。
それにしても、行革会議の議事録に目を通してみて痛切に感じることは、13人いる委員の中で全然発言しない委員、発言しても「各論反対」ばかりの委員、「不明瞭発言」の委員、同じ主張を蒸し返す委員、要するに委員としての適格性に疑問を感じさせる人が少なからずいたことだ。こういう委員の任命権者は橋本首相だが、実質的には誰れが人選したのだろうか。こういう委員の人選は、霞ヶ関では「トップシークレット」とされる。
行革会議の委員の場合、おそらく首相官邸の秘書官たちが総務庁の大臣官房などと相談して、無難な結論になるように人選したことだろう。その結果は、独立行政法人化の審議経過にみられたように、哲学なき場当たり対応の産物となったのである。
[ Kitazwa INDEX ]
ご意見・お問い合わせ│トップページ
Copyright NAGURICOM,2000

