沢栄の「さらばニッポン官僚社会」
| ■Online Journal NAGURICOM 沢栄の「さらばニッポン官僚社会」 |
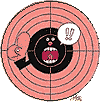
第78 章 哲学なき改革 / 三位一体改革
(2004年11月25日)
国と地方の関係を税財政面から見直す「三位一体改革」を巡り、中央省庁、地方自治体、自民党族議員を巻き込んだ壮絶な争いが繰り広げられている。この対立と混迷が深まるにつれ、改革ヴィジョンの欠如、国と族議員が握る補助金の地方支配力、反逆する地方の脆い財政実態が次々と浮き彫りにされてきた。
税財政改革が、理念を失った「税源の分捕り合戦」になってはならない。だが、最大の焦点となる自治体側の義務教育費国庫負担金の削減案(中学校教職員給与分8500億円)を巡る攻防は、皮肉なことに、この三位一体改革自体の理念なき危うさをさらけ出した。小泉首相は義務教育を国の責任においてきちんとやるべきか否かを、突き付けられた形だが、本来なら政府は国と地方のそれぞれの役割を明確にしたうえで改革に取り掛かるのがスジなのだ。数値目標だけ踊る、行き当たりばったりの改革手法が、異様な大混乱を引き起こした、といえる。
議論深めずに急展開
三位一体改革は、ある意味で「小泉改革」の性質をよく映している。「地方にできることは地方に」のキャッチフレーズ自体は、その通りだ。
問題は、国と地方自治体の基本的な役割確認と線引きを初めに行わずに走り出したことだ。初めから「哲学なき改革」であった。義務教育を含む国の補助金の削減とその分の税源委譲の案(いわゆる「片山プラン」)が2002年5月の経済財政諮問会議で発表され、そのわずか1カ月後の閣議決定で基本方針が決まった。このあと「補助金削減・地方への税源委譲、地方交付税のあり方見直し」を同時に進める三位一体改革の実現に向け、事態は急展開する。政府が議論を深めないまま、自治体側の考えで3兆円の補助金を削減せよ、と迫り、自治体側が急きょ具体案をまとめたためだ。
全国知事会など地方6団体が補助金削減の具体案の一つとして出したのが、都道府県が支払う公立小中学校の教員給与の半分を国が担う、義務教育費の国庫負担金のカットだ(06年までの第一期改革は中学校教員分のみ。第二期の09年度までに全廃)。ただし、全国知事会の場合、田中康夫長野県知事、片山善博鳥取県知事、石原慎太郎東京都知事ら13知事が、国庫負担金のカット反対を表明している。
ともあれ、義務教育のあり方について論議を尽くさずに地方6団体案が出され、これを小泉首相が「真摯に受け止める」と言明する一方、文部科学省と森喜朗前首相ら自民党文教族が強硬に反対する構図となる。
仮に地方案が通れば、戦後まもなくシャウプ勧告を受け一時は廃止したものの、知事・教育委員会の要請に押されて1953年から復活させ、今に至る「義務教育費国庫負担制度」が崩壊することになる。果たして、それでよいのか ―。
この是非を点検するには、1950年以後約3年続いた同負担制度の廃止期間に生じた「地方格差の拡大」と「教育条件の劣悪化」に目を向ける必要があろう。これが再び起こり得るかどうか。
文科省によれば、52年当時児童1人当たりの教育費は東京を100とすると茨城県で53と、差は約2倍に開いている。実学級当たりの教員数も小学校で負担制度廃止前の49年の1.22人から51年には1.20人に低下している。
教育の原点
義務教育費国庫負担制度は、そもそもは明治33(1900)年の市町村立小学校の教育費に対する国庫補助に始まる。大正7(1918)年には、義務教育費に対する国の負担責任を明確にする「市町村義務教育費国庫負担法」が施行され、この基本型が先の一時中断を経て今日まで続いてきたのである。
制度の中身は、市町村が小中学校を設置・運営するのに対し都道府県が教員を任命し、給与を負担するが、その給与実費の二分の一を国が負担する ― というものだ。全国の対象教員は約70万人、04年度予算額は2兆5128億円に上る。
義務教育費国庫負担金を削減しようという地方自治体の動きに仰天した文科省は、急きょことし4月に政令を公布し、「総額裁量制」を導入した。「教員給与の二分の一を国庫負担」など現行制度の維持を前提に、補助金の総額だけを国が決め、総額の枠内で自治体が自由に使える仕組みにした。従来は給料・諸手当の費目ごとに一定水準を超える額は国庫負担の対象外だったが、例えば総額の中で教職員数を増減したり、給与の種類や額も自由に決められる。国庫負担の対象外だった「少人数学級」も自治体の裁量で実現できる。
この総額裁量制により、文科省は補助金の使い方が自由になり、教員の実績・能力に応じた増給や非常勤講師を活用したユニークな少人数指導も可能になる、と期待した。だが、新制度の周知徹底が図られないまま、自治体側は一気に「負担金カット」に突き進んでしまったのだ。
朝日新聞の調査では、総額裁量制を利用している自治体は11にすぎず、残りの36都道府県は利用していない。「将来の活用を具体的に検討」と答えたのは8自治体のみ。自治体側の感度の鈍さが表れた。ただし、片山鳥取県知事のように「総額が確保され、使い勝手もよい」として、国庫負担金の削減より現状のほうがまし、とする意見もある。制度の存続で権限を保持しようと躍起の文科省と、税源委譲のため「義務教育費」を生けにえに捧げる自治体との、激しい攻防を物語る。
地域格差が必至
では、地方6団体の要求が通り制度が廃止された場合、教育現場にどんな影響がもたらされるか。
まず考えられるのは、教育の地方格差が広がることだ。この懸念に対し、自治体側は教育費の地方格差が生じることのないよう国の責任と併せ法令に明記すればよい、としている。
だが、地方の財政事情からみて、国庫負担金をなくして一般財源化すれば、地域格差がくっきり生じるのは自明の理だ。そうなれば憲法26条に定められた義務教育の機会均等制が揺らぐ。
このことは、一般財源で賄われている「学校図書整備費」をみれば想像がつく。小学校1校当たりの図書購入費に相当な格差が生じているからである。02年度ベースで見ると、全国平均40万円余に対し、トップ級の山梨県、神奈川県は約70万円だが、最下方の青森県、島根県は約20万円の水準。青森や島根の児童は、学校で本をたくさん読もうにも、山梨や神奈川に比べざっと3分の1弱しか手に入らないのだ。
しかも地方の財政はいま、急速に悪化している。国の交付税特別会計からの借入金残高と、地方債および公営企業債の残高を合計した地方借入金をみると、2000年度に188兆円だったのが、今年度末には204兆円に達する見込みだ。
今後の見通しは、官業の地方公社の相次ぐ破綻で一層悪化する。東京商工リサーチの調査によれば、この11月には大阪市の第三セクター「大阪シティドーム」と「クリスタ長堀」が、計900億円の負債を抱え大阪地裁に特定調停を申し立てた。大阪シティドームは大阪市が700億円を投じ、東京、福岡に続いて97年にオープンしたドーム球場。地元のプロ野球球団・近鉄の優勝で02年には赤字が縮小したものの、04年決算時には債務超過が137億円に上り、万事休した。他方、クリスタ長堀は97年にオープンした広い駐車場を備えた地下街だが、地価下落で賃料収入が低下し、14億円の債務超過に陥った。両社の再建計画は、自治体が巨大施設を購入するなど面倒をみるから、ゆくゆくは納税者の負担となる。
だが、これはほんの一例にすぎない。全国の土地開発公社の整理・解散は04年に入って急増している。既に50公社以上が破綻しているのだ。破綻ケースが目立つのは岐阜県、茨城県、愛媛県などだが、未整理の破綻予備軍を抱える自治体は草加市、安中市、伊丹市、池田市、北海道等、全国各地でおびただしい数に上る。
こうした自治体が、財源不足から苦しまぎれに教員の給与カットに走らざるを得なくなったとしても、不思議でない。そうなれば、義務教育の質に都道府県の格差が生じ、広がるのは避けられない。
地方公務員の高給ぶり
制度の是非を巡り、ほかに二つの要素を考える必要がある。
一つは、教育に取り組む海外諸国の動向だ。先進各国は近年むしろ教育予算の充実を図り、人材育成のため初等中等教育費を増やしている。義務教育の教員給与の全額を国が負担するケースも多い(フランス、イタリア、韓国、シンガポールなど)。
国内総生産(GDP)に対する先進主要国の同比率は、フランスの4%をトップに米、英、韓国が各3%台。日本はドイツの2.9%を下回る2.7%と最下位だ。「米百俵の精神」(小泉首相)と言ったところでカネをかけなければ、教育レベルを大きく向上させることはできない。国の責任において義務教育を高レベルに保つことが重要だ。
もう一つは、自分たちの自治体職員を国家公務員以上に優遇する放漫経営体質だ。自治体が「地方にできることは地方に」任せてほしい、と主張するなら、経費削減に向け自らエリを正さなければならない。でないと、義務教育にシワ寄せが来ることは必至だ。
総務省によれば、地方公務員の給与水準は平均して国家公務員よりも高い。その差は縮小傾向にあるとはいえ、職員の年令構成に合わせ国家公務員一般行政職を「100」として比較したラスパイレス指数でみると、指定都市の平均「102.2」をはじめ都道府県、市、特別区(東京都の区)ともに100を上回る(2003年4月時点)。国家公務員より低いのは町村の職員だけで、全地方公務員の平均は100.1。
都道府県と指定都市でみると、川崎、福岡、大阪をはじめ指定都市の給与高が目立つ。国家公務員より低いのは神戸、名古屋の2市だけ。東京都は102.5。47都道府県の地方公務員のうち、給与が国家公務員より低いのは5県にすぎない。
だが、国家公務員の運転手、守衛、用務員など「行政職(二)」とこれに相当する地方公務員の「技能労務職」を比べると、給与の差はもっと開く。なんと地方公務員のほうが国家公務員より21.7%も多いのだ。
こういう自治体の経営体質で、教育の責任をしっかり担えるだろうか。
田中長野県知事はことし8月、義務教育費国庫負担金について次のような見解を表明している。
「義務教育の実施そのものについては地方がその役割を担う必要があるが、実施にあたっての財源については、全国的な教育水準を維持するナショナルミニマムとして国の責任において保障すべきである。・・・義務教育の内容については、それぞれの地方についての自主性を尊重しつつも、最低限の内容を全ての児童が享受できる体制を確保すべきである」
その通りである。改革は、義務教育のあり方をしっかり論議するところから始めなければならなかったのだ。