沢栄の「さらばニッポン官僚社会」
| ■Online Journal NAGURICOM 沢栄の「さらばニッポン官僚社会」 |
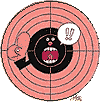
第69 章 「第二の特殊法人」爆発急増中 / 独立行政法人のまやかし
(2004年2月26日)
前月号でマナ板に乗せた特殊法人「雇用・能力開発機構」がこの3月、独立行政法人に移行する。結果、特殊法人改革の一環として2001年4月に独立行政法人(以下「独法」とも表記)制度が導入されて以来、その総数は95法人に達した。さらに4月には、全国の国立大学89校が独法化され「国立大学法人」になるほか、144の国立病院・療養所が一つの独法(国立病院機構)に統合される。整理される特殊法人、認可法人に代わって爆発急増中の独立行政法人。今回は、行革からほど遠い、そのまやかしの実態を取り上げる。
廃止・民営化と並ぶ行革手法
そもそも独立行政法人とは何か、から入ろう。ひと言でいえば、「廃止または民営化される」以外の特殊法人・認可法人に対して適用される行革手法で設立された法人である。つまり、特殊法人改革の対象となりながら「廃止または民営化」を免れた法人に対して独法化が行われるわけだ。
事は橋本龍太郎首相が96年11月に設置し、自らが会長を務めた首相直属の審議機関「行政改革会議」にさかのぼる。
1年後の97年12月、行革会議は1府21省庁から1府12省体制への中央省庁再編と内閣機能の強化、独立行政法人制度の発足を柱とする最終報告をまとめた。
この最終報告を受け、初の独法制度が2001年4月からスタートする。それは英国のマーガレット・サッチャー政権が取り入れた、政府の現業部門を政策の企画立案部門から分離独立させエージェンシー(外庁)とする「エージェンシー制度」を手本にしていた。
ところが、新藤宗幸・千葉大学教授(行政学)によれば、英国のエージェンシー制度は実は日本の特殊法人制度を見習って採用した制度であるという。だとすれば、日本側が有効な行革手法と考えたエージェンシー制度の導入をしたところで、特殊法人改革がうまくいくはずない。
事実、独法化のその後の経過は「第二の特殊法人」と化していったのである。
38特殊法人を独法化
橋本内閣時に導入が提唱された独法制度は以後、法制化(99年の独立行政法人通則法および各独法の個別法の成立)を経て、「廃止または民営化」と並ぶ特殊法人改革の手法として定着していく。
通則法によれば、「独立行政法人」とは ―
「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されない恐れがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として」設立される法人、だという。
次の森喜朗内閣は2000年12月に「行政改革大綱」を閣議決定し、特殊法人、認可法人の「廃止または民営化以外は独法化する方針」を表明。続く小泉内閣は、特殊法人改革を「小泉改革」の主要な柱と位置付け、わけても「道路四公団民営化」に力を注いだことは周知の通りだ。
しかし、道路公団改革の政府案は昨年12月に決着し、「官が焼け太る、まやかしの民営化」に終わっている(注)。
(注)道路公団改革が腰砕けになった理由は以下の通り。
政府案は―
- 民営化会社に必要な「経営の自律性」を認めず、通行料金から「利潤」を得ることも禁じた、
- 新会社が高速道路建設を採算性に基づいて自主的に決められず、国交省が新会社と協議して決める、建設を拒否したとしても、別の会社に頼むなど、建設できる仕組みにした、
- 資産(道路)を保有させ、借金を管理させる独立行政法人「保有・債務返済機構」を新設して永続化させ(解散は45年後)、公団の破綻責任を封印したまま天下り機関とした ― などのためだ。
小泉内閣は01年12月、政府系金融機関など一部の結論は先送りしたものの、特殊法人と認可法人の計163法人について整理合理化を閣議決定した。
この「特殊法人等整理合理化計画」で、38法人(統合して36)の独立行政法人化を決めている。改革対象法人の4分の1弱に相当する。別途整理が決まった各省庁の共済組合45を除けば、民営化(20)と統合・廃止(17)の数を上回った。
これを受け、2001年度に57法人が独法化されたのをスタートに、独立行政法人は雨後のタケノコのように増えていく。
特殊法人以上の天下り実態
国民負担の観点に照らして問題は、まず「第二の特殊法人」と呼ぶべき天下りのひどい実態だ。いや天下り比率は特殊法人を上回る。これは制度の適用を官に丸投げした結果だ。
昨年12月の政府発表によれば、独法の役員に占める退職公務員の比率は、92法人で全役員528人中236人と45%(特殊法人は39%)、うち毎月の給与を貰う常勤役員は397人中211人と53%(特殊法人は42%)を占める。
いや、特殊法人などの役員から独法に渡った者を含む「公務員もしくは準公務員出身者」でみると、独法の全役員のじつに96%に達するのだ。
役員報酬も、理事長で大半が本府省の局長並みの給与を貰う。
ところが、これら役員、職員の給与も退職金も、後述するように、例外の一法人を除いてすべて国の補助金(大部分は税金)で賄われているのだ。
そこから、官僚たちが 1. 独法を天下りの基地にし、2. 国民のカネを財源にする補助金によって高給を得ている ― という構図が浮かび上がる。予算の内容に立ち入って、問題をさらに掘り下げてみよう。
補助金から役員報酬
2003年度予算(計画ベース)をみると、独法62法人のうち国の補助金を受け取らず、自前で運営しているのは「日本貿易保険」だけ。残り61法人は役員らの人件費はすべて補助金から支給されている。
うち、人件費が突出している法人は、産業技術総合研究所(所管・経済産業省)を筆頭に、通信総合研究所(総務省)、家畜改良センター(農林水産省)、森林総合研究所(農水省)、物質・材料研究機構(文部科学省)など。
産業技術総合研究所(旧通産省工業技術院)は、職員数3200人近い独法で最大のマンモス法人だ。役員の年収も一番高く、理事長は東大と京大の学長のみが得られる国家公務員の最高俸給を上回る年収2650万円(のちに若干引き下げ)を受け取っていたことが、一昨年判明している。同研究所が交付される補助金も独法中最大で、予算額は初年度(2001年度)は846億8900万円、02年度875億8100万円、昨年度928億4200万円と、年々増えている。うち人件費は補助金の「運営費交付金」から賄われる。
同研究所の「運営費交付金」は昨年度684億1100万円。これに「施設整備費」の43億8500万円を加えた国の補助金は、約727億9600万円にも上る。
独法62法人全体では、役員、職員の人件費を含む「運営費交付金」(昨年度)は計2780億1100万円、「施設整備費」が計270億3400万円で、補助金総額は3050億4500万円。
今年度の財源措置をみると、雇用・能力開発機構を含む102法人に増えた結果、補助金は一般会計(税金)から2兆1905億4500万円、特別会計(雇用保険料など特別財源)から8313億6500万円に上る。独法の数とともに補助金も、跳ね上がっている。これら3兆円超の財源が、国民のカネで賄われるのだ。
加えて、法人側からの補助金請求はドンブリ勘定で通りやすい。独法は、事業の自律性が重んじられる建て前から、予算項目を一々積み上げて査定する特殊法人とは違い、事業予算は大まかに決められ、財務省の査定も甘い。法人側は、その予算を比較的自由に使うことができ、中期目標(3−5年)に向け次年度への繰越も可能な仕組みになっている。 高額な役員報酬と取りやすい補助金 ― そこから、二つの問題が立ち現れる。
一つは、これらの独法の「実績」をきちんと把握し(事後チェックし)、予算措置に反映されているかどうか。確たる存在理由がなければ、法人は即刻、廃止されなければならない。
二つめは、法人に存在理由があるなら、天下りを止めさせ「官の聖域」を民間に開放しなければならないが、政府にその決意はあるかどうかだ。
総務省の正念場
言うまでもなく、独法の存在意義を確かめるには、「実績」がきちんと評価される必要がある。巨額の国民のカネを使うのだから、確かな「業績評価」は当然の前提だ。独法の業績評価を行う各府省とダブルチェックする総務省の評価委員会(第三者機関)の評価対象法人数は、05年度には、なんと343法人に上る。国立病院機構の評価対象が144機関あるためだ。この大量の独法を評価委員は一々きちんと評価できるだろうか。
こうして「評価手法の確立」が、総務省幹部も言うように、いまや独法制度の最重要テーマに浮上してきたのである。一期生の独法以来、これまでに「評価」は2年にわたり行われたが、総務省も「不十分で評価方法はなお手探り状態にある」ことを認めている。企業が成果給制度を導入した場合の社員一人一人の「実績評価」と同じように、これは非常な難作業に違いない。
一つ、果たして「存在理由」があるのか疑問視されている文科省所管の法人「国立青年の家」のケースをみてみよう。
同法人は青年の団体宿泊訓練用の施設を設置し、青年の団体訓練を行い「健全な青年の育成を図る」ことを目的とする。なにやら全体主義的教練を思わせるが、文科省評価委員会の評価結果は「法人化一年目として(業務は)順調に滑り出したことは高く評価できます」などと、噦お墨付き器を与えている。評価の厳しさ、はまるで見えない。
これに対し総務省の評価委員会は「当該主催事業を継続的に実施することの必要性等についても、評価の結果を明示すべき」などと、余程まともな評価を行っている(『独立行政法人評価年報 平成14年度版』より)。
このケース一つとっても、府省の評価委員会の評価は噦身内意識器が働いて所管法人をかばいがち。「厳正な評価」にはなりにくい。その分、総務省評価委の第二次評価が重要性を増すが、委員は昨年までわずか12人しかいなかった。
これを今年は委員長、分科会長を除き委員20人体制に増員する方針だが、激増する独法に対応していくのは容易でない。総務省は、今年に続き来年も委員を増強する構えだが、他方で効果的な評価手法も確立しなければならない。独法制度をここできっちり軌道に乗せられるかどうか、いまや正念場に差しかかった、といえよう。
国民の側も、行革の成否と国民負担の両面から、独立行政法人の行く先に対し、監視の目を光らせていかなければなるまい。