沢栄の「さらばニッポン官僚社会」
| ■Online Journal NAGURICOM 沢栄の「さらばニッポン官僚社会」 |
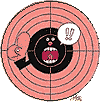
第67 章 崩壊の道路公団改革
(2004年1月13日)
「小泉改革」の主柱の一つが事実上、崩壊した。道路4公団民営化の政府案は、これに反発した民営化推進委員会(以下、「民営化委員会」)の改革派委員2人を辞任に追いやったが、その内容は「官僚と族議員の利益」に沿い、肝心要の「民営化」になっていない。民営化会社に必要な「経営の自律性」を認めていないためだ。小泉首相が民営化委員会立ち上げの際に指示した「上場できる企業」を目指そうにも、自立した経営は到底不可能だ。
「上下分離」を半永久化
政府・与党が決めた道路4公団民営化の枠組みは、見かけは民営化委員会の最終報告のいくつかの要素を取り入れてはある。形だけをみれば、民営化委員会の意見が「八割方尊重されている」(小泉首相)ようにも見える。だが、政府案は委員会の意見の要素を都合よく取り入れ、加工した。
最大の問題は、民営化委員会の最終報告に盛られた、道路資産・債務の保有と建設・管理の主体を分ける「上下分離」方式を焼き直し、変形させたことだ。これによって、官僚たちは「第2の特殊法人」と化した独立行政法人の「保有・債務返済機構」の永続化を可能にし、この機構を通じて新会社をコントロールできる仕組みをつくった。すなわち、民営化委員会が「発足後10年をめどに、新会社が機構の所有する道路資産を買い取り、機構は解散する」とした部分を「45年後」に置き換え、買い取り事項を外して、超長期の存続を確たるものにしたのだ。
この「45年後」の解散時期は、道路4公団の40兆円に上る借金の完済時期の「45年後」から来ている。その時点で、機構は解散して高速道路を国に移管し、無料開放する、というのだ。
だが、他方で国の高速道の整備計画(9342キロ)は変更せず、採算性が悪くなる道路を建設していくのだから、借金はむしろ膨らんでゆき、45年後に計画通り完済できない公算が高い。しかも、その頃には決定に関わった政府関係者は生存していないだろうから、責任問題も浮上せず、機構はさらに生き延びることになるだろう。このように機構の「45年存続保証」は、責任を棚上げにして官僚の天下り先を半ば永久化するものだ。
「公的ゴミ箱」
「上下分離」導入による官のメリットは、「第2の特殊法人」づくりにとどまらない。これにより、国民のカネ(財政投融資)から巨額の借金をして、事実上の破綻に陥っていた道路4公団の経営責任、ひいては道路行政の責任を、機構を隠れミノに隠しおおせるからだ。
4公団の財務は、4公団中最も優良とされた日本道路公団でさえ「会社更生法を適用する状態に限りなく近づきつつある」(近藤剛総裁の11月20日の記者会見)状況にある。
この破綻の責任官庁は、いうまでもなく、建設しか考えなかった国土交通省と財投から建設資金を供給し続けた財務省である。双方とも「上下分離」なら、4公団の膨大な借金を機構という公的機関の大鍋に流し込んでフタをしてしまえばよい(ある政府関係者は機構を「公的ゴミ箱」と呼んだ)。
事実、財投に大穴をあけた責任を逃れるため、財務省は早くから民営化委員会の一部委員に機構の創設を働きかけている。国民のカネが道路建設に注ぎ込まれて焦げ付いた事態を、国民に認識させないための工作だ。
財務省のめくらまし工作は、国交省と組んで民営化委員会の中間報告直前の02年8月頃から活発化し、「上下分離」は結局、報告に取り入れられる。今回の政府案は、このスキームを最大限に活用したものだ。
「上下分離」が固定すれば、新会社設立以後も借金が膨れ続けたところで、民間会社のように経営上行う借金の抑制は必要なくなるし、借金の責任問題も生じない。官や道路族にとって、まことに有難い“装置”になるのだ。このように「上下分離」の永続化こそが、政府案の中枢部を成しているのである。
国交省の下請け会社
もう一つ、見逃せないのは新会社(複数)に、民営化会社に不可欠の経営の自律性がまるで確保されていないことだ。新会社の自由な事業は、政府100%出資の完全子会社(特殊会社)として事実上、通行料金徴収や道路の清掃・補修、道路やサービスエリア、パーキングエリアを活用した新規事業に限られる。主要事業であるはずの道路建設は、自主的に行えない。なぜなら、「採算性に基づき自主的に決める」とした民営化委員会報告を無視して、「国土交通大臣が新会社と協議して建設を決める方式」を導入したためだ。新会社はいわば、国交省の下請け建設会社になるわけだ。
仮に、新会社が採算性を理由に建設を断ったら、大臣は別の会社に頼める。そこからも断られたら、大臣の諮問機関である社会資本整備審議会に諮って可否を判断する仕組みになっている。下請けが仕事を断ることはまずあり得ないが、万一の事態になっても、計画通り道路建設をやり遂げるように、ガンジガラメにしてあるのだ。
さらに悲劇は、新会社が通行料金の設定に当たって「利潤」が認められていないことだ。収支の差益分はそっくり機構に納めなければならず、機構はそれを4公団から受け継いだ大借金の返済に回すことになる。
なんのことはない、新会社は配当原資になる料金の利潤を手に入れられないのだから、仕事へのインセンティブは起こりようもない。
新会社は、自己調達資金で道路を建設するが、「政府保証」がなければ多額の借金はできないから、この点でも現行の公団(特殊法人)と実質変わらない。いや、ややこしい仕組みにして「第2の特殊法人」を増やし、国民に民営化の幻想を与えたことは、むしろ改革に逆行する。
丸投げ手法の限界
それにしても、「小泉改革」の象徴だった道路公団改革が、どうしてこうも無惨な結果に終わったのだろうか。
筆者は、小泉流の改革手法に大きな問題がある、とみる。改革方針は指示したが、成案作りを大臣などに丸投げして、審議が山場を迎えても迷走しても傍観している。民営化委員会の02年12月の最終報告の詰めの局面では、石原伸晃行革相(当時)が右往左往し、首相が傍観するなかで委員会が紛糾し、今井敬委員が委員長職を辞任した。03年5月の公団改革派の左遷人事に始まる日本道路公団の「幻の財務諸表」を巡る藤井治芳総裁(当時)の迷走でも、首相は動かず、扇千景国交相(当時)は藤井氏をかばい続けて混乱を大きくした。
そして、今回の政府決定でも、自民党に丸投げして民営化委員会報告の根幹部分を覆し、田中一昭委員長代理ら委員2人の辞任を招いた。
小泉流の丸投げ手法が、改革意欲に欠ける担当大臣のもと、官と族議員による改革案の骨抜きをもたらしたのである。
とはいえ、首相の「丸投げ」がもたらす「骨抜き」の危険を、首相自身が見抜けないはずはない。となると、首相の暗黙の承認のもとで、改革案が骨抜きされた疑いが浮上する。
そうだとすれば、改革は初めから虚構だったことになり、小泉首相は骨抜きを承知で「改革」をするフリをしていただけかもしれない。
骨抜きの結果は、官僚主導の新たな仕組みが出来上がってしまうだけに、深刻な後遺症を引き起こす。本来あるべき改革が歪められ、機構の創設のようにむしろ「改悪」された面もあり、改革の再トライを非常に困難にするためだ。旧構造に代わり、より巧妙に工夫された、改革ふうの新構造を廃棄するのは容易でない。
ここに「小泉改革」の幻想と国民の期待を裏切る罪がある。